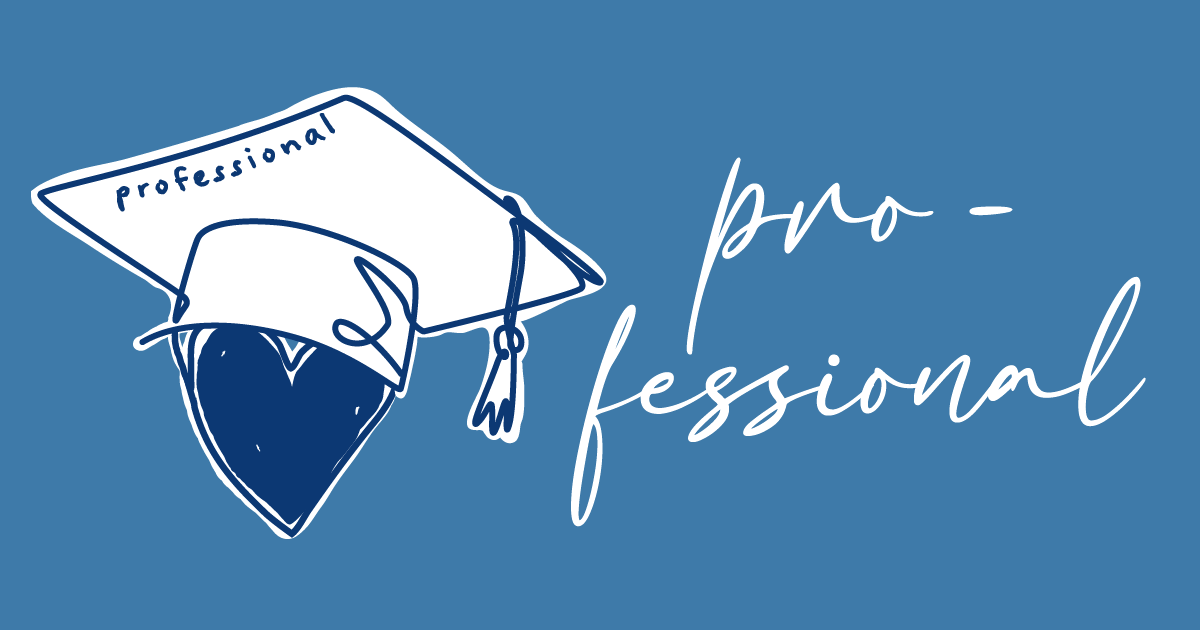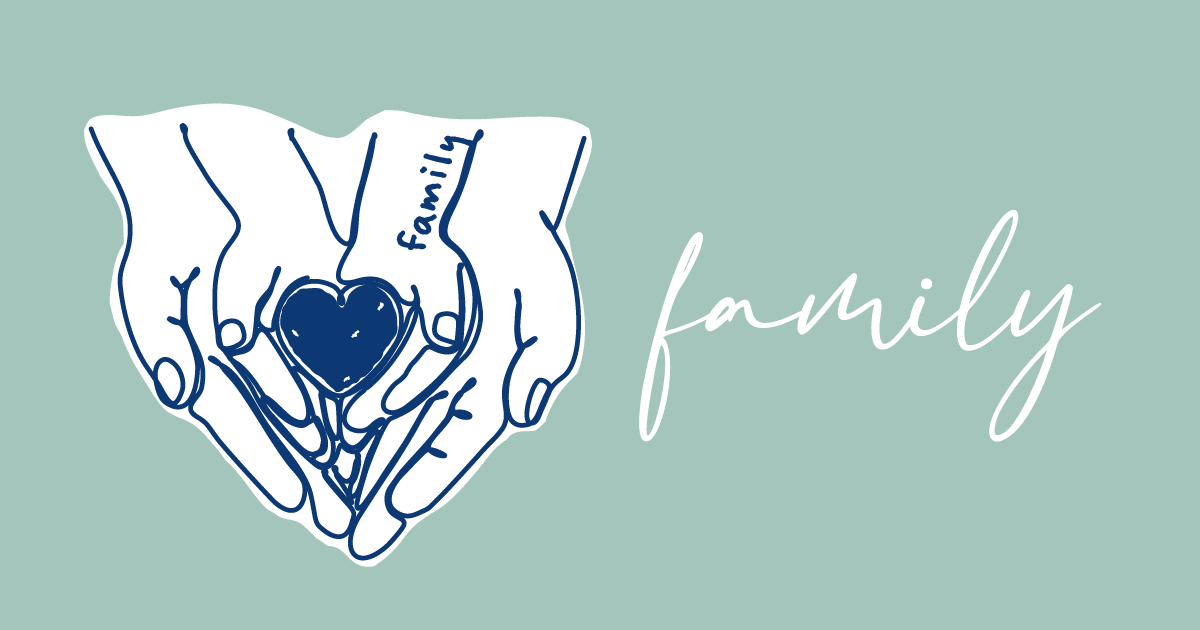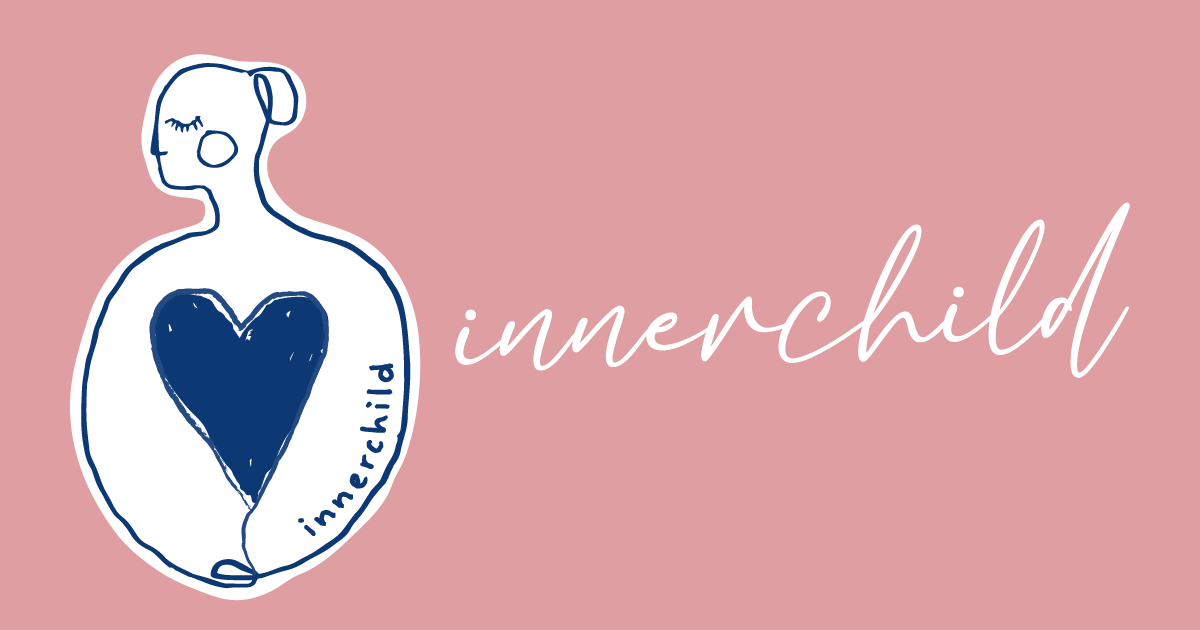ホメオパシーの「同種療法」とは?
ホメオパシーという言葉は、ハーネマンが古代ギリシャ語の単語、homoeo(=同じようなもの)と、pathos(=苦しみ・病気)を組み合わせてつくった造語です。
ホメオパシーは、日本語で「同種療法」とも呼ばれています。

その考えは古代ギリシャ時代までさかのぼります。
「同じようなものが、同じようなものを治す」といったのは医学の始祖ヒポクラテスです。
中世には、医師であり錬金術師でもあるパラケルススも同種療法について述べています。
錬金術と聞くと、怪しい!と思うかもしれませんが、ヨーロッパでの「錬金術師」の認識は、「化学者のはしり」なのです。
「同じようなものが、同じようなものを治す」とは?
なんだか不思議ですが、この同種療法というのは、わたしたち日本人にとっても、とても身近なものなのです。
日本には昔から、母から子へと代々、伝えられてきた、いわば〝おばあちゃんの智恵袋〟と呼ばれる民間療法があります。
喉がひりひり痛いときに、ショウガ湯を飲むことがありますよね。
ショウガ湯を飲むと喉がひりひりと熱くなります。このひりひりした熱さは、かぜをひいて喉がひりひりするときの症状と似ていますよね。これが、同じような症状を出すもので治すということです。
ぴりっとしたショウガ湯は熱くて、その〝ひりひり〟とした〝熱さ〟が、喉の〝熱っぽく〟て〝ひりひり〟した症状を治してくれるのです。
かぜをひいて熱が出たときには、卵酒を飲んで体温を上げたり、ふとんをたくさんかぶったりして、〝熱〟によって〝熱〟を追い出します。
ドイツには熱が出たときに熱い風呂に入るという民間療法もあるくらいなのです。
昔からの〝冷え性防止〟の健康法では、「毎日、お風呂からあがる前に冷水をかぶるとよい」とよくいわれます。
一瞬、全身がひやっとして鳥肌がたちますが、その後、体の芯からぽかぽかと自然に温まってきます。その温かさは、冷水をかけずに湯船からそのままあがったときよりも、ずっと持続します。またお風呂の後でなくても冷水をかぶると、同じようにその後に体が温かくなってきます。
これは体の自然な働きなのです。
冷えに対して、さらに水の冷たさを体に与えることによって、体は〝冷えている〟と認識します。そして体を温めようと、〝自己治癒力〟が働くのです。
同種療法の基本的な考え方
ホメオパシーというのは、体がアンバランスなときに、あえて同じようなアンバランスさを引き起こすものを与えます。
すると、体がそのアンバランスさに気がついて、元に戻そうと自己治癒力が触発されます。
これが同種療法の基本的な考え方なのです。


希釈振盪とは
ホメオパシーの創始者であるハーネマンは、物質の薬効(情報)のみを水に転写させる技術を研究し、発見しました。これを「希釈振盪(きしゃくしんとう)」と呼びます。

希釈振盪を何度も繰り返し、原物質の成分を含まない程希釈し、エネルギーパターンだけが活性化された液体を砂糖玉に垂らしたものがレメディーです。
希釈振盪はホメオパシー療法の根幹をなす革新的なテクノロジーです。この技術を通じて、物質のエネルギーは微細化され、生命体に働きかける力が最大限に引き出されます。